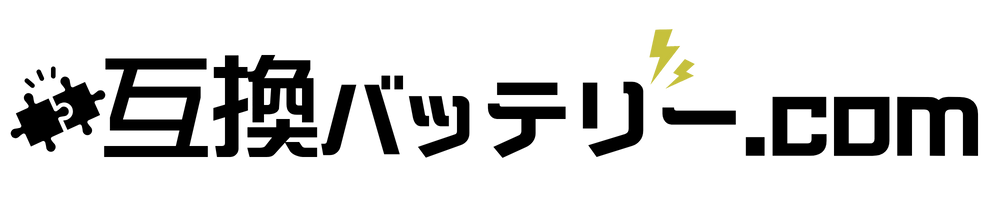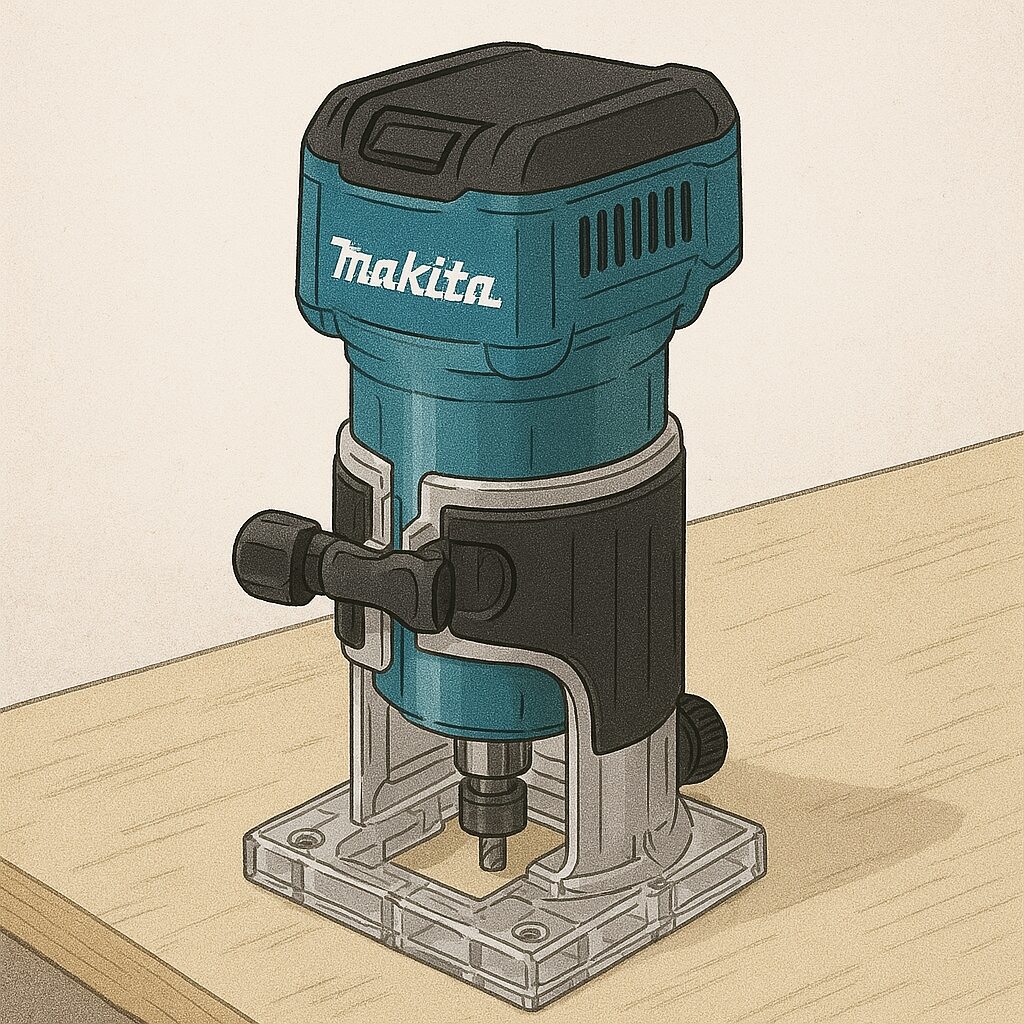マキタのトリマーは木材に面取り加工や溝掘りを行うのに欠かせない電動工具です。DIY愛好家からプロの木工職人まで幅広く愛用されていますが、初めて使う方にとっては「どのモデルを選べばいいのか」「ビットの種類と用途は何か」という疑問があるでしょう。本記事では、マキタトリマーの選び方から基本的な使い方、さらには18Vシリーズや3701シリーズなど代表的な機種のコツまで詳しく解説します。付属品の活用法やストレートガイドの正しい使用法、精度の高い溝掘りテクニックも紹介。さらに「ビットが入らない」「トリマーが動かない」といったトラブル時の対処法から、故障原因と対策、長く使うためのメンテナンス方法まで網羅しています。この記事を読めば、マキタトリマーを選ぶところから実際の使い方、トラブル対応までマスターできるでしょう。快適な木工作業のために、ぜひ参考にしてください。
記事のポイント
- マキタトリマーの機種別の特徴と適切な選び方
- ビットの種類と用途に応じた効果的な使い分け方
- 直線・円形などの様々な加工テクニックと付属品の活用法
- トラブル時の対処法と長持ちさせるためのメンテナンス方法
マキタトリマーの使い方と基本知識
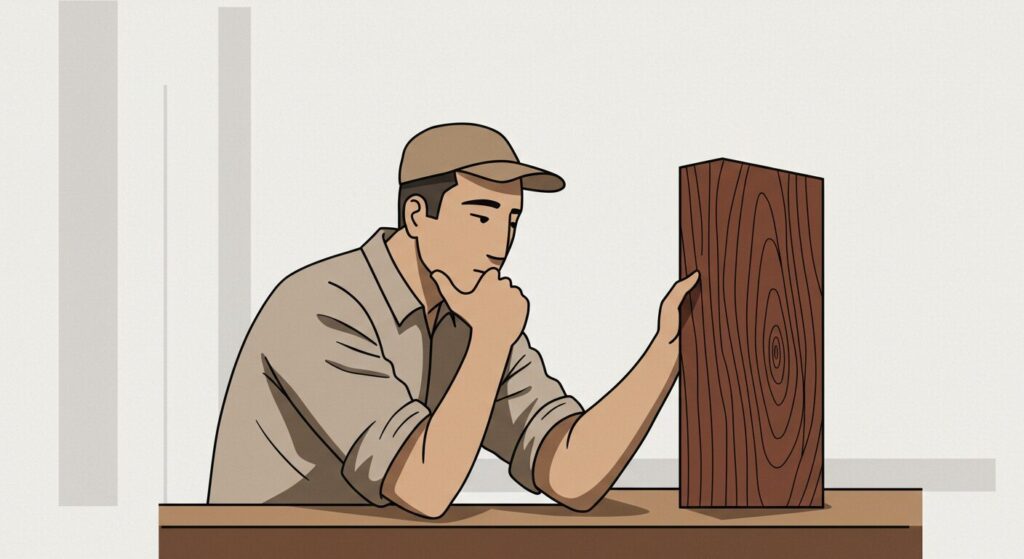
- マキタトリマー|選び方の重要ポイント
- マキタトリマー|ビットの種類と用途
- マキタトリマー|付属品の活用法
- マキタトリマー|ストレートガイドの使用法
- マキタトリマー|溝掘りのテクニック
マキタトリマー|選び方の重要ポイント
マキタのトリマーを選ぶ際は、作業内容や頻度に合わせた機種選びが重要です。特に初心者の方は、使いやすさを重視した選び方をおすすめします。
まず、電源方式で選ぶことが大切です。コード式は連続作業に向いており、価格も比較的安価です。一方、充電式(バッテリータイプ)は取り回しがよく、コンセントのない場所でも使用できますが、本体価格は高くなる傾向があります。
次に、出力と重量のバランスを確認しましょう。出力が高いモデルは切削能力が高い反面、重量も増します。長時間使用する場合は軽量モデルの方が疲れにくいため、作業内容に合わせて選択することが大切です。
また、操作性も重要なポイントです。マキタのトリマーには、深さ調整機構の違いがあります。M373やM3709シリーズはラックアンドピニオン式で直感的に操作できる一方、3707FCはネジ式でより細かい調整が可能です。
ビットの取り付け径も確認しておきましょう。マキタのトリマーは基本的に6mm径ですが、別売りのコレットを使用すれば6.35mm径にも対応できるモデルもあります。
予算や作業頻度に応じた選択も必要です。プロ向けの高性能モデルは耐久性に優れていますが、DIY用途であれば比較的安価なモデルでも十分な場合があります。初めてトリマーを使う方には、RT40DやM373など操作しやすいモデルがおすすめです。
マキタトリマー|ビットの種類と用途
マキタのトリマーのビットは用途によって多様な種類が揃っており、適切なビットを選ぶことで作業効率が大幅に向上します。それぞれのビットには特徴があり、加工目的に合わせて使い分けることが重要です。
ストレートビットは最も基本的なビットで、主に溝掘り加工に使用します。直線的な溝を掘るときに便利で、径のサイズは6mmが標準的ですが、作業内容によって異なるサイズを選べます。初めてトリマーを使う方は、まずこのビットから始めるとよいでしょう。
面取りビットには角面ビットと丸面ビットがあります。角面ビットは45度の角度で面取りができ、シャープな仕上がりになります。一方、丸面ビットは木材の角を丸く加工でき、優しい印象を与えるデザインに適しています。子供が使う家具など、安全性を考慮する場合に特に便利です。
装飾用のビットも充実しています。ひょうたん面ビットやギンナン面ビット、サジ面ビットなどがあり、それぞれ独特の装飾的な面取りができます。額縁や家具の装飾部分の加工に適していますが、一度に深く切削すると負荷が大きくなるため、数回に分けて少しずつ加工することをおすすめします。
特殊な用途には、V溝ビットやU溝ビット、アリ溝ビットなどがあります。V溝ビットは三角形の溝、U溝ビットは半円形の溝を掘ることができます。アリ溝ビットは引き出しなどの接合部に使う「ほぞ」を作るのに適しています。
また、ガイドベアリング付きのビットも便利です。フラッシュビットはテンプレートを使った型抜き加工に、目地払いビットは段差を均一に削るのに役立ちます。初心者の方でも安全に使えるように、ベアリングが木材をガイドしてくれる仕組みになっています。
マキタトリマー|付属品の活用法
マキタのトリマーには様々な付属品があり、これらを上手に活用することで作業の幅が広がります。基本的な付属品の特徴と使い方を理解することで、トリマーの性能を最大限に引き出せます。
ストレートガイドは最も基本的な付属品で、直線的な溝掘りや面取りをする際に必須です。木材の端に沿って平行に加工したい場合、このガイドを取り付けて使用します。調整は簡単で、木材からの距離を決めてチョウナットで固定するだけです。しかし、正確な加工をするためには、しっかりと木材に押し当てながら作業することが重要です。
テンプレートガイドは型板(テンプレート)を使った「ならい加工」に使用します。同じ形状を複数作りたい場合や複雑な形状を切り出したい場合に便利です。ただし、ガイドと実際の切削位置は約2mm異なるため、テンプレート作成時にこのズレを考慮する必要があります。
円切りガイドは円形の加工に使用します。多くの場合、ストレートガイドを組み替えることで円切りガイドとして使用できます。円の中心に釘やビスを打ち、そこを軸にトリマーを回転させることで円形にくり抜くことができます。ただし、加工できる円の大きさには制限があるため、大きな円を切りたい場合は自作の円加工治具を作ることをおすすめします。
トリマガイドとトリマシューは、トリマーベースに取り付けて加工精度を高める付属品です。トリマガイドは先端にコロ(ベアリング)があり、木材の側面に沿って加工する際に安定性を高めます。トリマシューは接地面積が広く、特に木端面の加工など、ベース面が不安定になりがちな作業で役立ちます。
ダストノズルは集じん機に接続して使用する付属品です。トリマー作業では多くの木屑が発生するため、こちらを活用することで作業環境を清潔に保ち、視界も確保できます。特に室内での作業では、ダストノズルの使用が推奨されます。
これらの付属品を上手に活用することで、トリマー作業の精度と効率が格段に向上します。初めは基本的なストレートガイドから始め、徐々に他の付属品も試していくことで、トリマーの可能性を広げていけるでしょう。
マキタトリマー|ストレートガイドの使用法
マキタのトリマーに付属しているストレートガイドは、直線的な加工を正確に行うための重要なアクセサリーです。正しく使用することで、初心者でも精度の高い作業が可能になります。
まず、ストレートガイドの取り付け方を確認しましょう。トリマー本体のベース部分にあるクランプスクリュを緩め、ガイドプレート部分を差し込みます。この際、ガイドの長さや木材との距離は、これから行う作業に合わせて調整しておくことが大切です。
ストレートガイドの位置調整は慎重に行う必要があります。ガイドと刃先の距離が、作業する溝の位置を決定するからです。チョウナットを緩めてガイドを移動できる状態にし、定規やスコヤを使って正確な距離に調整しましょう。位置が決まったらチョウナットをしっかり締めて固定します。
実際の使用時は、ガイドを加工材の側面にしっかりと押し当てることが重要です。この際、トリマーの送り方向に注意が必要です。基本的に、ビットの回転方向に対して抵抗が少なくなる方向に送ることで安全に作業できます。具体的には、トリマーを進める方向に対して、ガイドは右側に来るようにして加工します。
また、ストレートガイドを使う際の安全上の注意点もあります。作業前に必ずビットがしっかり固定されているか確認し、木材もクランプなどでしっかり固定しておきましょう。また、一度に深く切り込もうとせず、3mm以下の深さで複数回に分けて加工するのが安全です。
ストレートガイドは用途に応じてアレンジすることも可能です。例えば、ガイド面にはベニヤなどを貼り付けると、加工材に傷がつくのを防ぐことができます。また、ガイドの位置をずらして平行に複数の溝を掘ることも可能です。
さらに、自作ガイドを作ることで、ストレートガイドでは届かない、加工材の中央付近にも精度の高い溝掘りができます。シナベニアなどを2枚組み合わせ、上段のベニアの側面をガイド面として使用する方法が一般的です。
ストレートガイドを使いこなすことで、引き出しの底板や棚の背板をはめ込むための溝、装飾的な溝など、様々な加工が可能になります。少し練習すれば、プロのような精度の高い作業ができるようになるでしょう。
マキタトリマー|溝掘りのテクニック
溝掘りはトリマーの基本的な使い方の一つで、家具作りやDIYにおいて多くの場面で活用できるスキルです。マキタトリマーを使った溝掘りのテクニックを押さえておくことで、作業の質と効率が大幅に向上します。
溝掘りを始める前に、適切なビットを選択することが重要です。一般的に溝掘りにはストレートビットを使用します。ビットの径は加工したい溝の幅に合わせて選びますが、初めは6mm径のものから始めるとよいでしょう。必要に応じて、V溝ビットやU溝ビットも活用できます。
作業を始める前の準備も大切です。加工する木材はしっかりと固定し、作業ラインをあらかじめ墨や鉛筆で明確にマークしておきましょう。また、ビットの出る量(切削深さ)も適切に設定する必要があります。一度に深く切り込むと刃に大きな負荷がかかるため、複数回に分けて徐々に深くしていくことをおすすめします。
実際の溝掘り作業では、トリマーの送り方向が重要です。ビットは時計回りに回転しているため、トリマーを進める方向は、木材がビットの左側に来るようにします。これにより、反発力が少なく安定した加工が可能になります。
溝掘りの精度を高めるためには、ストレートガイドの使用が必須です。ガイドなしでまっすぐな溝を掘ろうとしても、必ずブレが生じてしまいます。ストレートガイドをトリマーに取り付け、加工材の端に沿わせることで、真っ直ぐな溝を掘ることができます。
加工材の端から離れた位置に溝を掘りたい場合は、自作のガイドが便利です。シナベニアなどを2枚使用し、上段のベニアの側面をトリマーのガイド面として、下段のベニアをベース面とする方法があります。この自作ガイドを使用すれば、木材の中央部分でも精度の高い溝掘りが可能です。
また、溝掘りのバリエーションとして、V字型やU字型の溝を掘ることもできます。V溝ビットを使えばV字型の溝が、U溝ビットを使えばU字型の溝が掘れます。これらの特殊な溝は、装飾的な効果を出したり、特定の接合方法に使用したりする場合に役立ちます。
溝掘り作業で最も重要なのは、安全に配慮することです。切削する深さを3mm以下にし、無理に押し付けず一定の速度で送ることを心がけましょう。また、常にトリマーのベース面を加工材にしっかりと密着させて作業を進めることが大切です。
これらのテクニックを実践し経験を積むことで、より複雑な溝掘り加工にも挑戦できるようになります。マキタトリマーを使いこなすことで、DIYや木工作業の可能性が大きく広がるでしょう。
マキタトリマーの使い方と上級テクニック

- マキタトリマー18V|使い方のポイント
- マキタトリマー3701|使い方のコツ
- マキタトリマー|ビットが入らない時の対処法
- マキタトリマー|動かない場合のチェック項目
- マキタトリマー|故障原因と対策
- マキタトリマー|分解とメンテナンス方法
マキタトリマー18V|使い方のポイント
マキタの18V充電式トリマー(RT40DやRT50Dシリーズなど)は、コードレスの利便性と十分なパワーを兼ね備えた人気モデルです。効果的に使いこなすためのポイントを押さえておきましょう。
まず使用前の準備として、バッテリーが十分に充電されていることを確認します。18Vバッテリーは作業量によって持続時間が変わるため、予備のバッテリーを用意しておくと安心です。また、本体とバッテリーの接続部に木屑などが付着していないかチェックすることも大切です。
18V充電式トリマーの大きな特徴は、速度調整ダイヤルがあることです。このダイヤルを使って回転数を6段階(約10,000〜30,000min⁻¹)で調整できます。硬い木材を加工する場合は低速から始め、様子を見ながら速度を上げていくことで、木材の焦げや刃の摩耗を防げます。
多くの18Vモデルには「待機スイッチ」という安全機能が搭載されています。これは誤作動を防ぐためのもので、待機スイッチを押してからON/OFFスイッチを操作する必要があります。最初は少し手間に感じるかもしれませんが、安全のために重要な機能です。
また、LEDライトが搭載されているのも18Vモデルの特徴です。このライトはビットの先端を照らし、作業精度を高めるのに役立ちます。薄暗い場所での作業や、細かいライン沿いの加工時に特に便利です。
バッテリー駆動のトリマーは連続使用時間に制限があるため、効率よく作業を進める工夫が必要です。事前に加工計画を立て、似た設定の作業をまとめて行うことで、調整の手間を減らせます。例えば、同じビットを使う加工を連続して行い、その後でビットを交換するといった具合です。
充電式トリマーは使い終わったらバッテリーを外しておくことをおすすめします。長期間使用しない場合は、バッテリーを40〜60%程度充電した状態で保管すると寿命を延ばせます。また、定期的にバッテリー端子の清掃も行いましょう。
18Vモデルはパワフルですが、一度に深く切り込むとモーターに負担がかかりバッテリー消費も早まります。3mm以下の深さで複数回に分けて加工する方が、結果的に効率よく作業できることが多いです。
このように、マキタの18V充電式トリマーは使い方を工夫することで、コード式に遜色ない性能を発揮します。取り回しの良さと十分なパワーを兼ね備えた道具として、DIYから専門的な木工作業まで幅広く活用できるでしょう。
マキタトリマー3701|使い方のコツ
マキタの3701シリーズトリマーは、コンパクトな設計と信頼性の高さで長く愛用されているモデルです。このトリマーを効果的に使いこなすためのコツをご紹介します。
3701シリーズの大きな特徴は、胴径が約60mmとスリムな設計であることです。このコンパクトさにより、片手でも持ちやすく、細かい作業も行いやすくなっています。しかし、片手だけで操作すると安定性が損なわれる場合があるため、基本的には右手で本体を保持し、左手でベース端部を押さえる両手操作をおすすめします。
電子制御機能を搭載している3701FCモデルでは、負荷がかかっても回転数が一定に保たれるため、安定した切削が可能です。この特性を生かすためには、トリマーを無理に押し付けず、一定の速度で送ることが大切です。無理に速く進めようとすると、かえって仕上がりが悪くなることがあります。
ビットの高さ調整は、3701シリーズの使いこなしにおける重要なポイントです。ベース部分のレバーを緩め、調整ローラーを押し回すことで行います。精密な作業が必要な場合は、スコヤなどを使ってビットの出る量を正確に測定するとよいでしょう。微調整が難しいと感じる場合は、少し浅めに設定してから徐々に深くしていく方法も効果的です。
実際の加工では、トリマーの送り方向に注意が必要です。ビットは時計回りに回転しているため、トリマーは常に手前から奥へと送ります。面取り加工の場合は、ビットの左側に加工面が来るようにトリマーを持ち、材料の端から内側へと動かします。この基本的な動きを守ることで、安全かつ美しい仕上がりが得られます。
3701シリーズには、透明なベースプレートが採用されているモデルがあります。これにより刃先が見やすく、正確な位置決めが可能になります。ただし、使用していくうちにベースプレートに傷がついて視認性が低下することがあるため、定期的なメンテナンスが必要です。
また、3701シリーズは集じん機に接続できる機能も備えています。木屑の飛散を防ぎ、作業環境を清潔に保つためにも、可能な限り集じん機を使用することをおすすめします。特に室内での作業や細かい加工では、視界確保のためにも集じん機の使用が重要です。
トリマー作業では安全面の配慮も欠かせません。作業前には必ず電源プラグをコンセントから抜いてビットの交換を行い、作業中は保護メガネや耳栓などの安全装備を着用しましょう。また、長時間の作業による疲労は事故の原因となるため、適度な休憩を取ることも大切です。
これらのコツを押さえることで、マキタ3701シリーズトリマーの性能を最大限に引き出せるようになります。コンパクトさと使いやすさを兼ね備えたこのトリマーは、正しく使えば初心者からプロまで幅広いニーズに応える優れた工具です。
マキタトリマー|ビットが入らない時の対処法
マキタのトリマーを使用していると、ビットがうまく入らないというトラブルに遭遇することがあります。このような状況は焦りがちですが、いくつかの対処法を知っておくことで簡単に解決できることが多いです。
まず最初に確認すべきなのは、使用しているビットの軸径がトリマーのコレットチャックに合っているかどうかです。マキタトリマーの多くは6mm径のビットに対応していますが、海外製のビットなどでは6.35mm(1/4インチ)径のものも多く、これらは直接取り付けられません。このような場合は、6.35mm用のコレットコーン(別売)を購入することで対応可能です。
次に、コレットナットやコレットコーンの状態を確認しましょう。長期間使用していると、木屑や汚れが蓄積してビットがスムーズに入らなくなることがあります。この場合、コレットナットを完全に外し、内部のコレットコーンも取り出して綺麗に清掃します。ブラシや圧縮空気を使うと効果的に汚れを除去できます。
また、コレットナットの締め付けが固くなり、手で緩められなくなっている場合もあります。無理に力を入れるとトリマー本体やコレットを損傷する恐れがあるため、付属のスパナを正しく使用することが重要です。シャフト固定用スパナをシャフトの溝にかませ、もう一方の手でコレットナット用スパナを反時計回りに回します。それでも緩まない場合は、スパナに軽く叩くような振動を与えると緩みやすくなることがあります。
ビットの軸部分にサビや傷がある場合も、挿入が困難になる原因です。このような場合は、細目のサンドペーパーやスチールウールで軽く磨いてから、再度挿入を試みましょう。ただし、強く磨きすぎると軸径が細くなりすぎて、今度はしっかり固定できなくなる可能性があるので注意が必要です。
コレットコーン自体が変形している場合もあります。これは通常、ビットを装着せずにコレットナットを強く締めたり、落下などの衝撃を受けたりすると発生します。変形したコレットコーンは修理が難しいため、基本的には交換が必要です。マキタの正規サービスセンターでパーツを購入するか、トリマー修理を依頼しましょう。
まれに、シャフトが曲がっている場合もあります。この場合、ビットを回転させたときに振れが生じます。シャフトの曲がりは素人修理が難しく、また安全上の問題もあるため、メーカー修理を依頼することをおすすめします。
これらの対処法を試してもビットがうまく入らない場合は、無理に使用せず、マキタのサービスセンターに相談することが最良の方法です。トリマーは高速回転する工具であるため、不具合があるまま使用することは事故につながる恐れがあります。
定期的なメンテナンスを行うことで、このようなトラブルの多くは未然に防ぐことができます。使用後はビットを取り外し、コレット部分の清掃を行う習慣をつけることで、トリマーを長く快適に使用することができるでしょう。
マキタトリマー|動かない場合のチェック項目
マキタのトリマーが動かなくなったときは、段階的なチェックを行うことで多くの場合解決できます。まずは焦らず、基本的な項目から確認していきましょう。
最初に確認すべきは電源の問題です。コード式トリマーの場合、コンセントに正しく挿し込まれているか、延長コードを使用している場合はその接続部分に緩みがないかチェックします。一方、充電式タイプであれば、バッテリーが充電されているか、正しく装着されているかを確認します。意外と多いのが、コンセントそのものに電気が来ていない場合です。別の電化製品を同じコンセントに接続して動作確認をしてみましょう。
次に確認すべきはスイッチの状態です。マキタのトリマーには、通常タイプと待機スイッチ付きの二段階操作タイプがあります。特に充電式の18Vモデルには、誤作動防止のための待機スイッチが搭載されていることが多いです。待機スイッチを押してからON/OFFスイッチを操作する必要があるため、この順序を間違えると動作しません。
また、過負荷保護機能が働いている可能性もあります。トリマーに過大な負荷がかかると、モーターやバッテリーを保護するために自動的に停止することがあります。この場合、一度電源を切り、冷却時間を設けてから再度電源を入れると復帰することが多いです。特に連続して硬い材料を加工した後や、深い切り込みを一度に入れようとした後に発生しやすい症状です。
コレットナットの締め付け具合も確認しましょう。締め付けが強すぎるとモーターに負荷がかかり、動作しなくなることがあります。逆に、ビットがしっかり固定されていないとモーターは回っているのにビットが空回りしている状態になります。コレットナットは適度な締め付け具合にすることが重要です。
コード式のトリマーの場合、コードの断線も考えられます。特にコード根元部分やプラグ付近は曲げ伸ばしの影響で断線しやすい箇所です。コードをゆっくり曲げながら動作を確認し、特定の角度でだけ電源が入るようなら断線の可能性が高いでしょう。
さらに、カーボンブラシの消耗も動作不良の原因となります。カーボンブラシはモーターの回転に電力を供給する部品で、使用とともに少しずつ摩耗します。正常なカーボンブラシは約10mm程度の長さがありますが、3mm以下になると交換が必要です。カーボンブラシは比較的安価で、自分で交換することも可能です。
これらのチェック項目を一つずつ確認しても解決しない場合は、モーター自体の故障や内部の電気系統の問題が考えられます。このような場合は無理に修理しようとせず、マキタの正規サービスセンターに相談することをおすすめします。
トリマーが突然動かなくなると焦りがちですが、多くの場合は上記のような基本的なチェックで原因を特定できます。定期的なメンテナンスを行うことで、トラブルの発生を未然に防ぐことも大切です。
マキタトリマー|故障原因と対策
マキタのトリマーの故障には様々なパターンがあり、それぞれに適した対策があります。故障の主な原因を理解し、適切な対処法を知っておくことで、トリマーの寿命を延ばし、修理費用を抑えることができます。
最も多い故障原因はカーボンブラシの消耗です。カーボンブラシはモーターに電力を供給する重要な部品で、使用に伴い少しずつ摩耗していきます。症状としては、動作が不安定になる、始動しにくくなる、使用中に停止するなどが挙げられます。カーボンブラシは消耗品として設計されており、自分で交換することも可能です。定期的に点検し、3mm以下になったら交換時期と考えましょう。
次に多いのが、過負荷による故障です。特に硬い木材を無理に加工したり、一度に深く切り込んだりすると、モーターに大きな負荷がかかります。この状態が続くとモーターが過熱し、内部の巻線が焼き切れる恐れがあります。過負荷を防ぐためには、切削深さを3mm以下に抑え、複数回に分けて加工すること、また高負荷の作業を続ける場合は適度に休憩を入れることが大切です。
粉塵の侵入もトリマーの故障原因となります。木工作業では大量の木屑が発生しますが、これがモーター内部に侵入するとベアリングやスイッチの不具合につながります。対策としては、作業中は集じん機を併用すること、また使用後は圧縮空気やブロワーでエア吹きを行い、通気口や隙間に溜まった木屑を除去することが効果的です。
落下や衝撃による故障も少なくありません。トリマーを落としてしまうと、ベアリングの破損やシャフトの曲がり、ハウジングのヒビなどが発生する可能性があります。特にシャフトの曲がりは振動や異音の原因となり、そのまま使用を続けるとさらなる故障につながります。作業台にはトリマーを置くためのスペースを確保し、使用後は専用のケースに収納することで落下のリスクを減らせます。
電気系統の不具合も考えられます。コード式のトリマーでは、コードの断線やプラグの接触不良が発生することがあります。また充電式モデルでは、バッテリー端子の接触不良やバッテリー自体の劣化が動作不良の原因となります。コードの取り扱いには十分注意し、無理に引っ張ったり鋭角に曲げたりしないようにしましょう。バッテリー端子は定期的に清掃し、バッテリー自体は適切な充電管理を行うことが大切です。
水濡れによる故障も致命的です。電動工具は基本的に防水設計ではないため、水分が内部に侵入すると電気系統のショートや錆の発生につながります。雨天時の屋外作業や水気のある場所での使用は避け、保管場所も湿気の少ない環境を選びましょう。万が一水濡れした場合は、すぐに電源を切り、十分に乾燥させてから使用することが重要です。
これらの故障原因を理解し、日頃から適切な使用と定期的なメンテナンスを心がけることで、マキタトリマーを長く安全に使用することができます。重度の故障や自分で対処できない場合は、無理せずマキタサービスセンターに相談することをおすすめします。
マキタトリマー|分解とメンテナンス方法
マキタのトリマーを長く快適に使い続けるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。基本的な分解とメンテナンス方法をマスターすることで、トリマーの性能を維持し、故障を予防できます。
メンテナンスを始める前に、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、バッテリーを取り外しておきましょう。また、作業中に小さなパーツを紛失しないよう、平らな場所で白い布やタオルの上で作業することをおすすめします。
まず取り組むべきなのは、ベースプレートの清掃です。ベースプレートはトリマーの精度を左右する重要なパーツで、使用していくうちに木屑や樹脂が付着します。ベースプレートの取り外しは、固定用のネジ(通常4本)を緩めて行います。取り外したベースプレートは、アルコールや専用のクリーナーを使って清掃しましょう。特に透明なベースプレートは、視認性を確保するためにも丁寧に磨いておくことが大切です。
次に、コレット部分のメンテナンスを行います。コレットナットを完全に外し、内部のコレットコーンも取り出して清掃します。微細な木屑がコレット内部に入り込むと、ビットがうまく固定できなくなる原因となります。コレットコーンは精密部品なので、変形させないよう注意しながら清掃しましょう。清掃後は薄く潤滑油を塗布すると、次回のビット交換がスムーズになります。
続いて、モーター部分の通気口の清掃を行います。通気口に木屑が詰まると冷却効率が低下し、モーターの過熱につながります。小さなブラシや圧縮空気を使って、通気口の木屑を除去しましょう。この際、木屑をモーター内部に押し込まないよう、外側から内側へではなく、内側から外側へ向けて清掃することが重要です。
カーボンブラシのチェックも定期的に行うべきメンテナンス項目です。カーボンブラシは通常、モーターハウジングの両側にキャップで固定されています。このキャップをマイナスドライバーで回して外し、カーボンブラシを取り出して長さをチェックします。約3mm以下になっていれば交換時期です。交換用のカーボンブラシは必ずマキタ純正品を使用しましょう。
高頻度で使用する場合は、内部グリスの点検も必要です。ギアボックス内のグリスは約200時間の使用で減少します。グリスの補充はある程度の技術が必要なため、自信がない場合はマキタサービスセンターに依頼するとよいでしょう。
また、スイッチ部分の動作確認も大切です。トリガースイッチやロックボタンがスムーズに動くか、また使用中にスイッチが勝手に切れたり入ったりしないかチェックします。スイッチの動きが悪い場合は、周囲に木屑が詰まっている可能性があるので、ブラシや圧縮空気で清掃しましょう。
メンテナンス後は、各部の固定ネジが緩んでいないか確認し、必要に応じて締め直します。また、コードの被覆に亀裂や擦れがないか、プラグに変形や焦げはないかもチェックしましょう。
こうした定期的なメンテナンスにより、マキタトリマーの寿命を大幅に延ばすことができます。作業の前後に簡単な点検を行う習慣をつけることで、突然のトラブルを防ぎ、いつでも最良の状態でトリマーを使用することができるでしょう。
マキタトリマーの使い方のまとめ:基本から応用まで

- 電源方式は作業環境に合わせてコード式か充電式(18V)を選択する
- ビットは6mm径が標準だが、コレットを交換すれば6.35mm径も使用可能
- 切削深さは3mm以下に設定し、複数回に分けて加工するのが基本
- ビットの回転方向は時計回りのため、トリマーは手前から奥へと送る
- 面取り加工時はビットの左側に加工面が来るように材料に対して配置する
- ストレートガイドは木材の端から平行に加工する際に必須のアクセサリー
- 自作ガイドを使えば木材中央部でも精度の高い溝掘りが可能になる
- テンプレートガイドは型板を使った「ならい加工」に使用する
- 円切りガイドで円形の加工が可能(ストレートガイドを組み替えて使用)
- 18Vモデルは速度調整ダイヤルで回転数を用途に合わせて調整できる
- 充電式モデルは予備バッテリーを用意すると長時間作業に対応できる
- 精度の高い加工には両手操作(右手で本体、左手でベース端部)を心がける
- コレットナットの締め付けはスパナを正しく使用して適切な強さで行う
- 使用後は木屑を清掃し、特に通気口や隙間の粉塵をしっかり除去する
- カーボンブラシは3mm以下になったら交換時期と考える