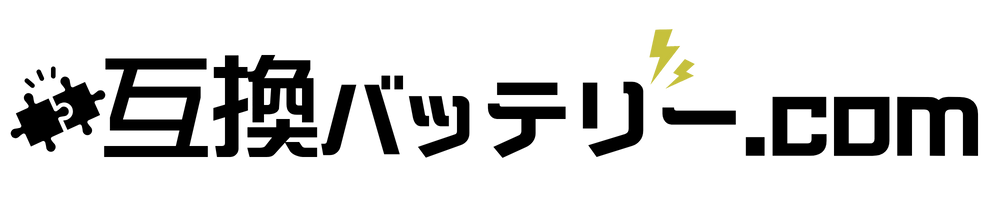最近ニュースでモバイルバッテリーの発火事故をよく目にしますよね。Ankerやcheeroといった有名メーカーでさえリコールを発表しており、手持ちの製品が発火の原因にならないか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
実はリチウムイオン電池の発火事故は年々増加傾向にあり、正しい知識を持っていないと一覧にあるようなリコール対象製品を使い続けてしまうリスクがあります。今回は発火事故を起こしたメーカーの事例や中華製バッテリーの危険性、そして安全な製品の選び方について詳しく解説していきます。
記事のポイント
- 発火事故を起こした主要メーカーと具体的なリコール対象製品
- なぜ有名メーカー製でも爆発や発火事故が起きてしまうのか
- Amazonなどで売られている危険な中華製バッテリーの見分け方
- 発火リスクの低い安全な日本製メーカーのおすすめ機種
モバイルバッテリーで発火したメーカーと主な事故原因
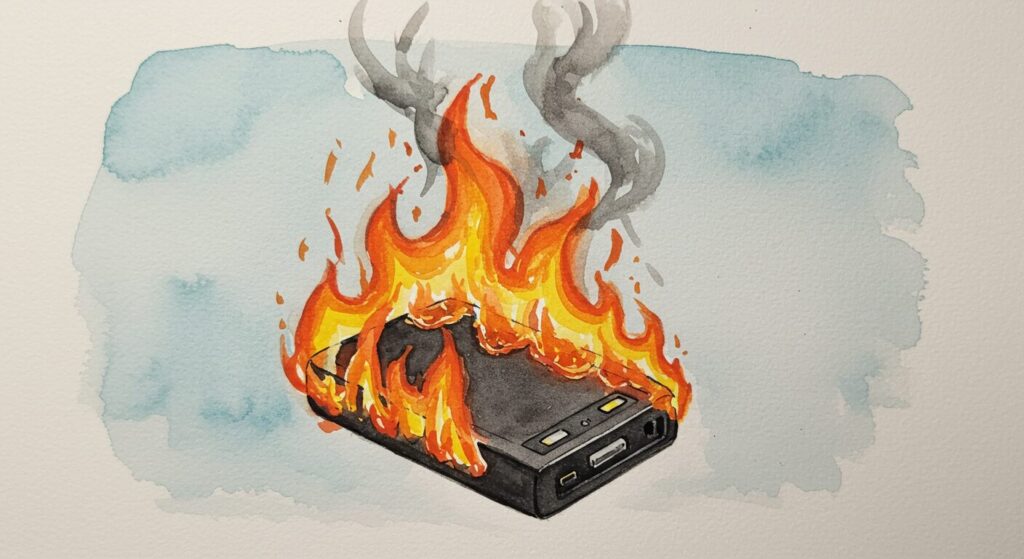
ここでは、実際に発火事故や大規模なリコールが発生したメーカーの情報を整理します。ニュースで話題になったあのメーカーから、意外な企業の製品まで、事故の実態とその背景にある原因を詳しく見ていきましょう。
発火事故を起こしたメーカー一覧とリコール情報
2025年現在、モバイルバッテリーの発火事故やそれに伴うリコールは増加の一途をたどっています。消費者庁や経済産業省の情報を元に、リコールを実施した主なメーカーと対象製品をまとめました。もしお手持ちの製品が該当する場合は、直ちに使用を中止してください。
主なリコール実施メーカーは以下の通りです。
| メーカー | 主な対象製品 | 概要と原因 |
|---|---|---|
| Anker (アンカー・ジャパン) | PowerCore 10000など多数 | セル製造工程での異物混入による内部短絡リスク |
| cheero (ティ・アール・エイ) | cheero Flat 10000mAh | 製造委託先の品質管理不備、部材への湿気侵入 |
| CIO (シーアイオー) | SMARTCOBY Ex01など | バッテリーセルの製造不良(負極スラリーの問題) |
| Xiaomi (シャオミ) | 33W Power Bank 20000mAh | 特定のリチウムポリマーセルの不良 |
| IKEA (イケア) | VARMFRONT | 製造不良による発火の可能性 |
これらの製品は、内部ショートによる熱暴走のリスクが確認されています。特にここ数年は、これまで信頼性が高いとされていた大手メーカーでも、製造委託先(サプライヤー)の管理ミスによる事故が目立ちます。
リコール対象製品は、メーカー公式サイトや消費者庁のリコール情報サイトでシリアルナンバーを確認できます。「自分は大丈夫」と思わず、必ず型番を確認する癖をつけましょう。未対応のまま使い続けることが、火災事故への最短ルートになってしまいます。
Ankerなどの主要メーカーで多発する発火事例
モバイルバッテリー界の最大手とも言えるAnkerですが、2025年には複数回にわたる大規模なリコールを実施する事態となりました。特に衝撃的だったのは、ベストセラーモデルである「PowerCore 10000」を含む約100万台規模の回収です。
報告されている事故の内容は深刻です。
- 米国では19件の火災および爆発報告があり、軽度の火傷や物的損害が発生。
- 日本国内でも充電中に発火する事例や、愛知県や静岡県でソファ周辺が焼損する火災が発生。
原因は、サプライチェーンの上流にあたる電池セル製造工場での「異物混入」でした。製造過程で微細な金属片などが混入することで、バッテリー内部でショート(短絡)が起き、それが熱暴走を引き起こして発火に至ります。
Anker製品は非常に人気があり信頼も厚いですが、異なる製造ラインやサプライヤーの部品が混在することで、特定のロットにだけ不具合が生じるケースがあるという点は覚えておく必要があります。
過去に発火事故があったcheero等の対応状況
ダンボーデザインなどで人気を博したcheero(ティ・アール・エイ)でも、重大な発火事故が発生しています。「cheero Flat 10000mAh」という製品では、リコール発表後も回収が進まなかった結果、2025年7月にJR山手線の車内で発火し、乗客が負傷するという痛ましい事故が起きました。
この事例から私たちが学ぶべき教訓は、リコールの周知と回収の難しさです。
- 事故原因:従来とは異なる製造委託先での品質管理不備。安全基準を満たさない部材が使われ、湿気が浸入してショートした。
- 対応状況:2019年から販売され、2023年にリコールが開始されましたが、回収率は1割にも満たない状態でした。
メーカー側も必死に回収を呼びかけていますが、ユーザー情報登録がない店頭販売などの場合、個別の連絡が届きません。この事故を受けて、鉄道会社や消防庁も注意喚起を強化しています。cheeroに限らず、CIOやBelkinなども含め、各社とも不具合が発覚した際は迅速にリコールを発表し、返金や交換対応を行っています。
中華製のモバイルバッテリーは危険性が高いのか
Amazonや楽天で検索すると、聞いたことのないブランドの激安モバイルバッテリーがたくさん出てきますよね。いわゆる「無名の中華製バッテリー」は危険なのでしょうか。
結論から言うと、品質管理がずさんな製品に当たる確率は高いと言わざるを得ません。今回のAnkerやXiaomiのリコール問題でも明らかになったように、大手メーカーでさえ中国の電池セルサプライヤー(例:Apex社など)の部品不良に悩まされています。
- PSEマークがない、または偽造の疑いがある:日本の電気用品安全法の基準を満たしていない可能性大。
- 異常に安く、容量が過大表示されている:「50000mAhで2000円」など、物理的にありえないスペック。
- サポート窓口がない:発火しても連絡がつかず、泣き寝入りになるケースが多い。
もちろん、中国製=すべて悪ではありません。AnkerやXiaomiも中国系企業ですが、彼らはリコール対応を行う責任能力があります。一番怖いのは、「売り逃げ」を前提としたノーブランド品や、リコール対応すらしない悪質な業者の製品です。
爆発や発火の原因となるリチウムイオン電池の仕組み
なぜモバイルバッテリーは爆発したり発火したりするのでしょうか。その原因のほとんどは、バッテリー内部の「制御不能な熱暴走」にあります。
リチウムイオン電池は、正極と負極の間をリチウムイオンが移動することで電気を蓄えます。この正極と負極は「セパレータ」という薄い膜で隔てられていますが、以下のようなトラブルでこの膜が破れると、内部でショート(短絡)が起きます。
- 製造不良(異物混入・バリ):今回のAnkerやCIOの事例。金属片などがセパレータを突き破る。
- 外部からの衝撃:落下させたり、カバンの中で圧迫されたりして物理的に損傷する。
- 過充電・過放電:保護回路が正常に働かず、限界を超えてエネルギーを溜め込む。
一度ショートして熱が発生すると、化学反応が連鎖的に加速し、数百度の高温になって発火・爆発します。膨張しているバッテリーは内部でガスが発生している危険信号ですので、絶対に使用を続けてはいけません。
モバイルバッテリーの発火したメーカーと安全な選び方
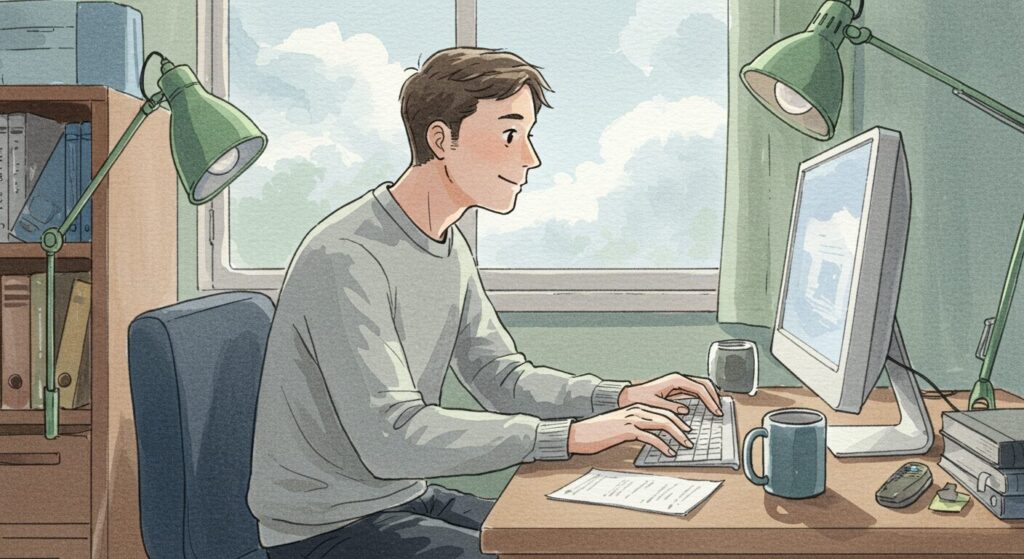
ここまで怖い話が続きましたが、モバイルバッテリーは生活必需品です。ここからは、リスクを最小限に抑え、安心して使える製品を選ぶための具体的なポイントを紹介します。
発火しない安全な日本製メーカーのおすすめ製品
「絶対に発火しない」と言い切ることは難しいですが、限りなくリスクが低い選択肢として、日本のメーカーが管理・販売している製品をおすすめします。彼らは日本の厳しい安全基準(PSE)をクリアするだけでなく、独自の厳格な品質管理を行っています。
私が特におすすめする安全性の高いメーカーは以下の3社です。
- ELECOM (エレコム):リコール事例がなく、非常に信頼性が高いです。特に「釘刺し試験」でも発火しない安全性を確認したモデルや、熱暴走しにくい「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用した製品もラインナップされています。
- BUFFALO (バッファロー):国内設計で安定性が高く、発火報告を聞きません。家電量販店でも定番で、サポート体制もしっかりしています。
- MOTTERU (モッテル):神奈川県のメーカーで、品質へのこだわりが強いです。2年保証がついている製品も多く、デザイン性と安全性を両立しています。
特に、これからのスタンダードになりつつある「リン酸鉄リチウムイオン電池」や「全固体・半固体電池」を採用したモデルは、構造的に発火しにくいため、少し価格が高くても選ぶ価値があります。
Amazonで買ってはいけない危険な商品の特徴
AmazonなどのECサイトは便利ですが、玉石混交です。危険な商品を避けるための「フィルター」を自分の中に持ちましょう。
避けるべき商品の特徴は以下の通りです。
- ブランド名が読めない・コロコロ変わる:大文字のアルファベットの羅列だけのブランドは、同じ商品を名前を変えて売っているだけのことが多いです。
- 「令和最新版」「超大容量」などの煽り文句:検索対策のキーワードを詰め込んだだけの商品は、品質よりも売ることを優先しています。
- レビューの日本語が不自然:「サクラ」による高評価レビューで星の数を稼いでいる可能性があります。星1つや星2つの低評価レビューをチェックし、「発熱した」「溶けた」という報告がないか確認してください。
価格だけで選ぶと、家を燃やすリスクを買うことになりかねません。「安物買いの銭失い」どころか、「命失い」にならないよう注意が必要です。
消費者庁のリコール情報で対象製品を確認する方法
自分が持っているモバイルバッテリー、あるいはこれから買おうとしている製品がリコール対象かどうかを調べるには、消費者庁のリコール情報サイトが最も確実です。
手順は簡単です。
- 「消費者庁 リコール情報サイト」にアクセスする。
- 検索窓に「モバイルバッテリー」や「リチウム電池内蔵充電器」と入力する。
- 該当するメーカーや型番がないかチェックする。
また、経済産業省のサイトでも重要な注意喚起が行われています。リコール対象製品は、メーカーが無償交換や返金を行っています。「面倒だからいいや」と放置せず、必ず手続きを行ってください。それはあなただけでなく、周囲の人の安全を守ることにもつながります。
不要になった発火リスクのある電池の捨て方
「膨張して怖いから捨てたい」「リコール対象だったけど交換手続きが面倒だから処分したい」と思った時、絶対にやってはいけないのが「燃えるゴミ」として捨てることです。
ゴミ収集車の中で圧縮された際にモバイルバッテリーが押し潰され、発火して車両火災になる事故が頻発しています。
正しい処分の手順
家電量販店やホームセンターにある「小型充電式電池リサイクルBOX」に入れます(※ただし、JBRC加盟メーカー製に限る場合や、膨張・破損したものは断られる場合があります)。
多くの自治体では「有害ごみ」や「特定品目」として回収しています。膨張したバッテリーの扱いについては、必ずお住まいの自治体のホームページで確認してください。
Ankerなどは自社製品の回収キットを用意している場合があります。
リコール品の場合は、メーカーが着払いで回収してくれるケースがほとんどですので、まずはメーカーの案内を確認しましょう。
ランキングで見る安全性の高い人気メーカー
最後に、いま選ぶべき安全性の高いメーカーを、私の独断と偏見、そして市場の評価を交えてランキング形式で紹介します。各メーカーの「これを買っておけば間違いない」というイチオシ製品もピックアップしました。
1位:ELECOM (エレコム)
安全性重視なら間違いなし。多重保護回路に加え、温度検知機能も優秀。日本のメーカーとしての信頼感は頭一つ抜けています。
おすすめモデル:EC-C03BK(薄型モデル)
「ナトリウムイオンは高いけれど、安全な国内メーカー製がいい」という方に最適な、Amazonでのベストセラーモデルです。スマホと重ねて持ちやすい薄型デザインで、過充電や過熱を防ぐ多重保護回路をしっかり搭載しています。リコール事故も報告されておらず、コスパと安全性のバランスが非常に良い一台です。
2位:Anker (アンカー) ※ただし最新の対策済みモデルに限る
リコールはありましたが、その後の対応や製品改良のスピードは世界トップクラス。公式サイトでリコール対象外であることを確認できれば、性能はピカイチです。
おすすめモデル:Anker Nano Power Bank
Anker製品を選ぶなら、リコール騒動以前の古いモデルではなく、管理体制が見直されたこの最新モデル(A1259)を選んでください。USB-Cケーブルが本体に内蔵されているため、ケーブルを忘れる心配がありません。Anker独自の保護システム「ActiveShield 2.0」で温度管理も強化されています。
3位:MOTTERU (モッテル)
「発火しない」だけでなく「長く使える」ことを重視。サポートが手厚く、女性にも持ちやすいデザインが多いのも魅力です。
おすすめモデル:MOT-MB10001
「重いのは嫌だ」という方におすすめの、国内最小・最軽量クラス(約174g)のバッテリーです。神奈川県の日本メーカーが品質管理を行っており、発火事故の報告もありません。丸みを帯びたデザインは衝撃を逃がしやすく、物理的な破損による発火リスクも考慮されています。
モバイルバッテリーで発火したメーカーの総括と対策
モバイルバッテリーは非常に便利な反面、エネルギーの塊であることを忘れてはいけません。2025年は多くのメーカーで発火事故やリコールが相次ぎましたが、これは私たち消費者にとっても「安全」を見直す良い機会です。
まとめとして、以下の3点を心に留めておいてください。
- リコール情報は他人事ではない:Ankerやcheeroなどの有名製品も対象になっています。必ず型番確認を。
- 「謎の中華」は避ける:リスクを回避するなら、ELECOMなどの国内メーカーや、サポート体制の整ったブランドを選ぶ。
- 異変を感じたら即中止:「熱すぎる」「膨らんでいる」は危険信号。もったいないと思わず、直ちに使用をやめて適切な方法で処分する。
安全なモバイルバッテリーを選んで、快適なスマホライフを送りましょう。あなたの命と財産を守れるのは、あなた自身の正しい選択だけです。