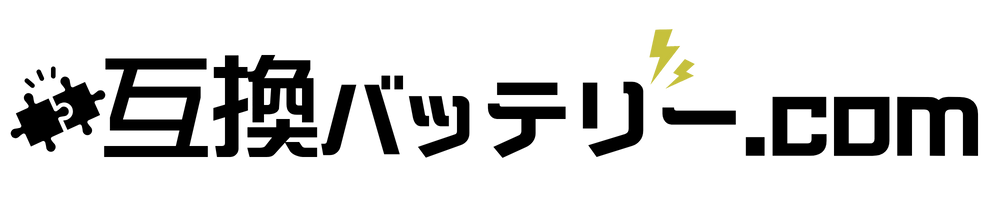近年、作業現場の効率化と清潔さを両立させるための重要なツールとして、マキタの集塵機が注目されています。特にBluetoothを活用したAWS無線連動システムは、コードレス工具と集塵機をシームレスに連携させる革新的な技術として、多くの専門家から高い評価を得ています。
この記事では、マキタのAWS無線連動とは何か、そのワイヤレスユニットの使い方と設定方法、さらには各種無線連動タイプの特徴を詳しく解説します。18V、40V、100Vと電源タイプが異なる製品の比較や、Bluetooth接続方法、小型集塵機の魅力、そして既存製品へのBluetooth機能の後付け方法まで幅広くカバーしています。
また、初めてマキタの集塵機を購入する方向けに、選び方のポイントやおすすめのセット構成についても紹介します。作業環境や用途に最適なマキタ集塵機ブルートゥース対応モデルを見つけ、効率的で快適な作業環境を実現するための情報が満載です。現場のプロもDIY愛好家も、このガイドを参考にすれば、自分に最適な集塵機を選ぶことができるでしょう。
記事のポイント
- マキタのAWS無線連動システムの基本概念と動作原理
- 電源タイプ別(18V、40V、100V)の集塵機の性能比較と特徴
- ワイヤレスユニットの設定方法とBluetooth接続の手順
- 作業環境や用途に応じた最適な集塵機の選び方とおすすめセット
マキタのBluetooth(ブルートゥース)対応集塵機の基本と選び方

- マキタのAWS無線連動とは何か
- ワイヤレスユニットの使い方と設定方法
- マキタの集塵機|無線連動タイプの種類
- マキタの集塵機|選び方のポイント
- マキタの集塵機|Bluetoothの接続方法
マキタのAWS無線連動とは何か
マキタのAWS(Auto-start Wireless System)は、Bluetoothを活用した電動工具と集じん機の無線連動システムです。2017年8月に発売されたこの技術により、コードレス工具でも集じん機と連動させることが可能になりました。
従来の集じん機連動は電源コード付きの電動工具に限られていました。工具側のコンセントを集じん機に接続し、電源供給を検知して連動を行う方式でしたが、この方法では充電式のコードレス工具と連動させることができませんでした。また、電源容量の問題から集じん機の吸い込み力を上げられないという課題もありました。
AWSシステムでは、Bluetoothによって電動工具の動作を無線信号で発信します。これにより充電式工具との連動が実現し、さらに電力供給の問題も解消されたため、集じん機側もフルパワーで稼働できるようになりました。作業現場では電源コードが絡まる心配もなく、取り回しの良さも大幅に向上しています。
ただし、AWS無線連動を使用するためには、対応する電動工具と集じん機、そして専用のワイヤレスユニットが必要です。初期投資としてこれらをすべて揃える必要がある点はデメリットと言えるでしょう。
ワイヤレスユニットの使い方と設定方法
マキタのワイヤレスユニット(A-66151)は、AWS対応電動工具と集じん機を無線連動させるために必要な専用Bluetoothレシーバーです。使用方法は非常にシンプルで、以下の手順で設定できます。
まず、集じん機のスイッチを「AUTO」の位置に設定します。次に、集じん機のBluetoothスイッチを緑色に点滅するまで押し続けます。続いて、電動工具側にワイヤレスユニットを装着し、同様にLEDが点灯するまでボタンを押してペアリングを完了させます。この操作により、電動工具の動作に応じて自動的に集じん機が連動するようになります。
ワイヤレスユニットは一度ペアリングしておけば、対応工具間で差し替えながらの使用も可能です。今後AWS対応工具を追加購入する場合、ワイヤレスユニットを買い足して各工具に取り付けておくと、差し替えの手間なく使用できて便利です。
なお、ワイヤレスユニットは別売りとなっているため、AWS対応の電動工具や集じん機を購入する際に、ワイヤレスユニットも一緒に購入する必要があります。工具本体ではなくバッテリー側にワイヤレスアダプタを装着する方式の方が合理的ではないかという意見もありますが、現状ではワイヤレスユニットを工具側に取り付ける仕様となっています。
マキタの集塵機|無線連動タイプの種類
マキタの無線連動対応集じん機は、電源タイプによって大きく3種類に分けられます。それぞれの特徴を把握して、作業環境や用途に合わせた選択が重要です。
まず、AC100V電源タイプの集じん機(例:VC0840)があります。電源が確保できる環境では、バッテリー切れの心配なく継続的に使用できます。このタイプは無線連動だけでなく、従来のコンセント連動にも対応しているため、お持ちのAC電動工具も活用できる利点があります。
次に、18V×2本(36V)バッテリータイプの集じん機(例:VC867DZ)です。コードレスで使用でき、作業場所を選びません。吸込仕事率は75Wで、一般的な作業には十分なパワーを発揮します。バッテリーBL1860B使用時には、吸込み力最大で約40分の連続使用が可能です。
最後に、40Vmax(36V)バッテリータイプの集じん機(例:VC002G)があります。最大吸込仕事率は205Wと高く、36V機と比較して約2.7倍のパワーを持っています。さらに防じん防滴性能(IP54)も備えており、粉塵や雨の中でも安心して使用できます。
これらの無線連動タイプはいずれも、ワイヤレスユニットを装着した対応電動工具と連動して自動的に起動・停止します。作業効率を高めたい方や、コードレスでスッキリとした作業環境を求める方に特におすすめです。
マキタの集塵機|選び方のポイント
マキタのBluetooth対応集塵機を選ぶ際は、主に「電源タイプ」「集塵容量」「対応工具との相性」の3つのポイントに注目すると良いでしょう。これらを押さえることで、自分の作業環境に最適な機種を見つけることができます。
まず電源タイプについては、AC100V電源タイプとバッテリータイプがあります。電源が確保できる作業場所が多い場合は、AC100V電源タイプ(VC0840など)がおすすめです。電源切れの心配がなく、長時間の作業にも対応できます。一方、電源の確保が難しい現場や移動が多い作業では、バッテリータイプ(VC867DZやVC002Gなど)が適しています。特に40Vmaxタイプは高いパワーと長時間の稼働が魅力です。
次に集塵容量については、8Lと15Lの2種類が主流です。頻繁に粉塵を捨てるのが面倒な場合や、一度の作業で多くの粉塵が発生する場合は、15L容量の機種が便利です。マキタの8Lと15Lの集塵機はサイズや価格に大きな差がないため、無理のない範囲で15L容量を選ぶと作業効率が上がるでしょう。
最後に対応工具との相性です。AWSシステムを活用するためには、電動工具側もAWS対応製品である必要があります。すでにAWS対応の電動工具をお持ちの場合は、同じくAWS対応の集塵機を選びましょう。また今後の買い足しや買い替えも考慮し、同一のバッテリータイプで統一すると便利です。
なお、乾湿両用タイプと粉じん専用タイプの違いも重要です。水などの液体も吸引する予定がある場合は乾湿両用タイプを、乾いた粉塵のみを扱う場合は粉じん専用タイプが適しています。粉じん専用タイプはフィルターの目が細かく、微細な粉塵をしっかり捕集できるメリットがあります。
集塵機の購入はそれなりの投資になるため、現在の作業内容だけでなく、将来的な使用シーンも想定した上で選ぶことをおすすめします。
マキタの集塵機|Bluetoothの接続方法
マキタの集塵機とBluetooth対応電動工具を無線連動させる方法は非常にシンプルです。初めて行う場合でも、以下の手順に従えば簡単に設定できます。
接続の前提条件として、集塵機がAWS(Auto-start Wireless System)対応モデルであること、そして電動工具側にワイヤレスユニット(A-66151)が装着されていることが必要です。これらの条件が揃ったら、実際の接続作業に移りましょう。
まず集塵機側の準備として、スイッチを「AUTO」の位置に合わせます。これは自動運転モードを意味し、無線連動の前提となります。次に集塵機のBluetooth連動ボタンを、LEDが緑色に点滅するまで押し続けます。この状態で集塵機はペアリング待機状態となります。
続いて電動工具側の設定です。ワイヤレスユニットが正しく装着されていることを確認し、ユニット上のボタンをLEDが点灯するまで押します。ここで集塵機と電動工具のペアリングが完了し、両者の無線連動が確立されます。
この設定が完了すると、電動工具のスイッチをONにした時に自動的に集塵機も起動し、OFFにすると集塵機も停止するようになります。ホースだけで繋がれた状態になるため、コードの絡まりや引っかかりがなくなり、作業効率が大幅に向上します。
ペアリングは一度行えば記憶されるため、毎回設定し直す必要はありません。ただし、1台の集塵機に複数の電動工具をペアリングする場合は、使用する工具ごとにペアリング操作が必要になります。また、ワイヤレスユニットを別の工具に付け替える場合も再度ペアリングが必要です。
なお、何らかの理由でペアリングがうまくいかない場合は、電源を入れ直してから再度試すか、他の電子機器からの干渉がないか確認してみることをおすすめします。
マキタのBluetooth(ブルートゥース)対応集塵機の製品比較

- マキタの集塵機|Bluetooth18V対応製品
- マキタの集塵機|Bluetooth40V対応製品
- マキタの集塵機|Bluetooth100V対応製品
- マキタの小型集塵機|Bluetooth対応モデル
- マキタの集塵機|Bluetooth機能を後付けする方法
- マキタの集塵機|Bluetooth対応のおすすめセット
マキタの集塵機|Bluetooth18V対応製品
マキタの18V対応Bluetooth集塵機は、コードレスでありながら十分な吸引力を持ち、移動の多い現場で重宝します。代表的なモデルとしてVC867DZが挙げられます。
VC867DZは18Vバッテリーを2本使用する36V仕様の集塵機で、AWS無線連動に対応しています。最大吸込仕事率は75Wと、コードレス集塵機としては十分なパワーを備えています。騒音レベルも抑えられており、従来機と比較して吸込仕事率が10Wアップしながらも、騒音は1dB低下しています。この低騒音化は、風窓形状の排気口を大きくして風速を下げ、風切り音を低減する設計によるものです。
リチウムイオンバッテリー18V×2本を使用した場合の連続使用時間は、吸込み力最大「5」で約40分、最小「1」で約100分(BL1860B 6.0Ah使用時)となっています。1度の充電で十分な作業時間を確保できるため、短時間~中時間の作業に適しています。
また、このモデルは「自動チリ落とし機能」を搭載しています。スイッチのON/OFFの度に自動でチリを落とす「ギュッパフィルタ」により、強い吸引力が長時間持続します。具体的には、スイッチONでプレフィルタがパウダフィルタに密着し、スイッチOFFで元に戻ることで粉じんを落とす仕組みです。
このほか、VC665DZという6L容量の背負式集塵機もラインナップされています。最大吸込仕事率85Wで、メッシュ素材のベルトを採用し、汗によるムレを抑えつつ体にフィットする設計となっています。背負式なので両手が自由に使え、高所作業や狭い場所での作業に便利です。
なお、これらの製品は本体のみの販売(バッテリー・充電器別売)が基本となっているため、別途バッテリーと充電器を用意する必要があります。すでにマキタの18V製品をお持ちの方であれば、同じバッテリーを流用できるメリットがあります。
マキタの集塵機|Bluetooth40V対応製品
マキタの40V対応Bluetooth集塵機は、高いパワーと長時間稼働を両立した最上位モデルです。特に代表的なのがVC002GとVC004Gの2機種で、いずれも無線連動AWS対応モデルとなっています。
VC002Gは8L容量、VC004Gは15L容量の集塵機ですが、基本性能は共通しています。最大の特徴は40Vmaxバッテリーとハイパワーブラシレスモータの組み合わせにより、最大吸込仕事率205Wを実現している点です。これは従来の36V(18V+18V)機と比較して約2.7倍のパワーアップを意味し、強力な吸引力を必要とする現場に最適です。
バッテリーは1本でも使用可能な2本並列取付タイプとなっており、状況に応じて柔軟に運用できます。バッテリー1本での使用時は出力が制限されますが、急な作業でもバッテリー1本あれば使用可能な点は実用的です。
また、本体はIP54、バッテリーはIP56の防じん防滴性能を備えているため、粉塵や雨でも安心して使用できます。屋外作業や悪条件下での作業が多い方にとって、この耐環境性能は大きな強みとなるでしょう。
さらに注目すべきは、VC009GZという40Vmax対応の背負式集塵機もラインナップされている点です。集塵容量は2Lと小さめですが、質量が4.3kgと軽量で、背負うことで機動性高く作業できます。風量調整や無線連動の操作は手元スイッチで行えるため、作業を中断することなく効率よく使用できます。
40Vmax対応モデルは18V対応モデルと比較して価格が高めですが、パワー・耐久性・バッテリー持続時間のすべてにおいて優れています。長時間の連続作業や、パワーを必要とする現場で活躍するプロフェッショナル向けの選択肢と言えるでしょう。
マキタの集塵機|Bluetooth100V対応製品
マキタのBluetooth対応100V集塵機の代表モデルはVC0840です。このモデルは電源の取れる現場で使用することを前提としていますが、Bluetooth無線連動機能を備えている点が大きな特徴です。
VC0840の最大の魅力は、コードレス工具との無線連動と従来のAC工具との連動の両方に対応している点です。無線連動対応の充電式工具と使えば配線がスッキリし、従来のAC工具とも連動コンセントを使って連携できます。このハイブリッド性により、新旧の工具を効率よく活用できるため、徐々に工具を買い替えていく過程でも便利に使用できます。
パフォーマンス面では、最大吸込仕事率220Wを誇り、コードレスモデルよりも安定した高い吸引力を発揮します。電源容量の問題がないため、常にフルパワーで集塵できるのもメリットです。さらに吸込み力調整ダイヤルを装備しており、1~5の間で無段階に調整が可能です。これにより、素材や作業内容に応じた最適な吸引力で作業できます。
また、VC0840にもON・OFFの度に自動でチリ落としを行う機能が搭載されており、強い吸引力が持続します。スイッチオンでプレフィルタがパウダフィルタにギュッと密着し、スイッチオフでパッと戻ることで粉じんを落とす仕組みは、長時間の作業でも吸引力の低下を抑える効果があります。
ただし、バッテリーモデルと異なり電源コードが必要なため、コードの引き回しや電源の確保が必要になります。また、重量は約7.4kgとなっており、頻繁な持ち運びには少々重たく感じるかもしれません。
これらの特性から、VC0840は固定した作業場所や、電源が確保できる現場での長時間作業に最適です。特に、まだAWS対応のコードレス工具をすべて揃えていない方や、AC工具も併用したい方にとって、理想的な選択肢となるでしょう。
マキタの小型集塵機|Bluetooth対応モデル
マキタからは小型でも高機能なBluetooth対応集塵機がいくつか販売されています。特に注目すべきは背負式モデルのVC265DZとVC009GZです。これらは携帯性と機動性を重視する現場作業に最適な選択肢となっています。
VC265DZは18V×2本(36V)バッテリー仕様で、集塵容量2L、質量4.5kgの軽量コンパクト集塵機です。ブラシレスモータ搭載により、最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現しており、小型ながらもしっかりと粉じんを吸引できます。体にフィットして動きやすく、作業の疲労を軽減する設計となっています。さらに0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集するHEPAフィルタを採用し、クリーンな排気を実現しています。
一方のVC009GZは40Vmax仕様の背負集塵機で、集塵容量は紙パック使用時2L、ダストバッグ使用時1.5Lです。質量は4.3kgと非常に軽く、背負った状態での長時間作業も苦になりません。パワー面では最大モード3で165Wの吸込仕事率を発揮し、小型ながら強力な吸引力を誇ります。風量調整・無線ボタン・無線連動・バッテリ容量の確認は手元のスイッチで操作でき、作業効率向上に貢献します。
このほか、コンパクトタイプとしては、マキタのR30Y3(SC)も注目に値します。このモデルはHiKOKIブランドですが、2022年末に発売されたR3640DAはHiKOKI製品として小型集塵機クラスで初のBluetooth連動に対応した機種です。集塵容量は約6Lで、従来品と比べてターボモード時の吸込仕事率が約1.8倍に向上している点が特徴です。
小型集塵機を選ぶ際のポイントは、バッテリーの持続時間と機動性のバランスです。長時間作業が予想される場合は、予備バッテリーを用意するか、容量の大きいバッテリーと組み合わせることをおすすめします。また、背負式モデルは両手が自由に使えるため、高所作業や狭い場所での作業に適しています。
なお、いずれの小型モデルもワイヤレスユニット(A-66151)を別途購入する必要があります。本体にはワイヤレスユニットが同梱されていない点に注意しましょう。
マキタの集塵機|Bluetooth機能を後付けする方法
マキタの既存集塵機にBluetooth機能を後付けする方法として、WUT02 AWS Adaptorが海外では販売されています。このアダプターを使用すれば、従来の連動コンセント式の集塵機でもAWS無線連動が可能になります。
WUT02はAC連動集塵機のACコンセントに差し込んで使用するアダプターです。WUT02とペアリングすることで、AC連動の集塵機でもAWS対応電動工具との無線連動が可能になります。ただし、WUT02自体にはBluetoothアダプタが内蔵されていないため、別途ワイヤレスユニット(A-66151)を取り付ける必要があります。
しかし残念ながら、この製品は2023年時点で日本では正式に販売されていません。規格対応や電圧の違いなどが理由と考えられますが、将来的には日本市場でも販売される可能性があります。
一方で、HiKOKIではマキタとは異なるアプローチでBluetooth後付けを実現しています。HiKOKIはバッテリー自体にBluetoothを内蔵するBluetooth対応バッテリーを提供しており、このバッテリーを装着するだけで無線連動機能が使えるようになります。具体的には、BSL36A18B(36V-2.5Ah/18V-5.0Ah)と大容量版のBSL36B18B(36V-4.0Ah/18V-8.0Ah)の2種類が展開されています。
マキタ製品に直接この手法を適用することはできませんが、HiKOKIの例からもわかるように、バッテリー側にBluetooth機能を持たせるアプローチは理にかなっています。マキタも将来的にはバッテリー内蔵型のBluetooth対応モデルを検討する可能性があるでしょう。
現状でマキタ製品にBluetooth機能を後付けする公式の方法はありませんが、AWS対応集塵機(VC0840など)を新規購入し、既存の電動工具にワイヤレスユニットを装着するという部分的な更新は可能です。このアプローチなら、すべての工具を一度に買い替える必要がなく、段階的にAWS環境に移行できます。
なお、非公式な改造や互換品の使用はメーカー保証外となり、安全面でもリスクがあるため推奨できません。公式の製品リリースや販売開始を待つことをおすすめします。
マキタの集塵機|Bluetooth対応のおすすめセット
マキタのBluetooth対応集塵機と電動工具を同時に導入する場合、セットで購入すると効率的です。特におすすめのセット構成をいくつかご紹介します。
まず初めてAWS無線連動システムを導入する方には、AC100V集塵機VC0840と18V充電式防じん丸ノコKS513DZ、そしてワイヤレスユニットA-66151の3点セットがおすすめです。このセットの魅力は、集塵機がAC電源なので長時間安定して使用できること、同時に従来の有線連動にも対応しているため既存の電動工具も活用できる点です。KS513DZはブラシレスモーターを搭載し、最大切込深さ47mmの高性能モデルです。このセットがあれば、コードレス環境と従来環境の両方で効率的に作業ができます。
次に、完全コードレス環境を構築したい方には、40Vmax充電式集塵機VC002Gと40Vmaxコードレス電動工具(HS002G丸ノコなど)、ワイヤレスユニットA-66151のセットが理想的です。40Vmaxシリーズは高いパワーと長時間稼働を両立し、電源のない現場でも安心して使用できます。特にVC002Gは最大吸込仕事率205Wと強力で、従来の36V機と比較して約2.7倍のパワーを発揮します。また、防じん防滴性能(IP54)も備えており、屋外作業にも適しています。
また、コンパクトさと機動性を重視する方には、18V×2本充電式背負集塵機VC265DZと、対応する18V電動工具(CJ36DA充電式ジグソーなど)、ワイヤレスユニットA-66151のセットもおすすめです。背負式集塵機は両手が自由に使えるため、高所作業や狭い場所での作業に最適です。
いずれのセット構成でも、ワイヤレスユニットA-66151は必須となります。このユニットを通じて集塵機と電動工具が無線連動するため、忘れずに購入しましょう。また、充電式モデルの場合はバッテリーと充電器も別途必要になる場合があるため、製品仕様を確認することが重要です。
既存の工具との共存や将来の拡張性も考慮し、自分の作業スタイルに合ったセット構成を選ぶことで、AWS無線連動システムの恩恵を最大限に活かせるでしょう。
マキタのBluetooth(ブルートゥース)対応集塵機で知っておくべきポイント

- AWS(Auto-start Wireless System)は2017年8月に発売されたBluetoothによる無線連動システム
- コードレス工具と集じん機を無線で連動させることが可能
- 電力供給の問題が解消され集じん機側もフルパワーで稼働可能
- 使用には対応電動工具と集じん機、専用ワイヤレスユニット(A-66151)が必要
- ワイヤレスユニットは工具側に取り付ける仕様
- 集じん機のスイッチを「AUTO」にしてBluetoothボタンを押してペアリング設定
- 電源タイプは「AC100V」「18V×2本(36V)」「40Vmax」の3種類がある
- AC100V電源タイプ(VC0840)は有線連動と無線連動の両方に対応
- 18V×2本タイプ(VC867DZ)はコードレスで吸込仕事率75W、最大40分使用可能
- 40Vmaxタイプ(VC002G)は吸込仕事率205Wと高い防じん防滴性能(IP54)を備える
- 背負式モデル(VC265DZ、VC009GZ)は携帯性と機動性に優れている
- 海外では後付け用WUT02 AWS Adaptorも販売されているが日本では未販売
- 集塵機の容量は主に8Lと15Lがあり、サイズと価格に大きな差はない
- 粉じん専用タイプはフィルターの目が細かく微細な粉塵を捕集
- 初心者には集塵機VC0840と丸ノコKS513DZ、ワイヤレスユニットのセットがおすすめ